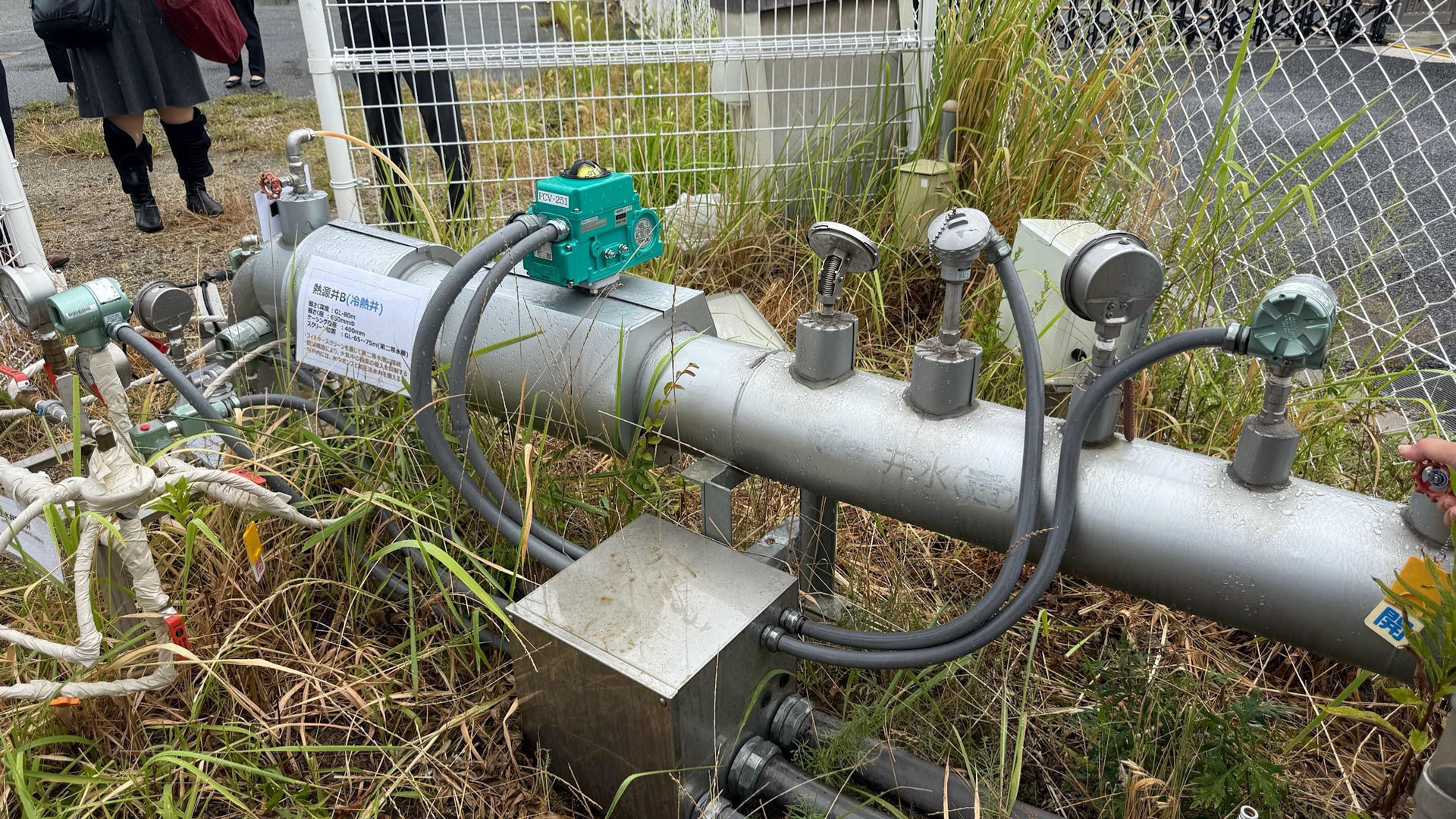写真)可動式営農型太陽光発電の実証の様子(設置場所:岐阜大学、設備メーカ-:株式会社ガリレオ)
出典)中部電力株式会社電力技術研究所「農業と発電の両立 可動式営農型太陽光発電の最適アルゴリズムの開発」
- まとめ
-
- 可動式営農型太陽光発電は、農業生産と発電を両立させ、食料安全保障とエネルギー自給率向上に貢献する技術。
- 高エネルギーX線回折による非破壊評価は、ガスタービン高温部品の劣化状態を非破壊で検査し、保守・運用コスト削減と安全性向上に寄与する。
- これらの革新的な技術は、日本の食料安全保障とエネルギー自給率向上の課題を解決し、基幹産業の効率的かつ安定的な運用に貢献する。
電力会社と関連協力企業や研究機関、大学などによる研究成果を公開する「テクノフェア2025」(主催:中部電力株式会社技術開発本部)が今年も開催された。取材をして興味深かった複数のテーマを2回に分けて報告する。
1 農業と発電の両立を追求:可動式営農型太陽光発電の挑戦
農地の一部分に太陽光パネルを設置し、発電をおこないながら同時に農業生産を続ける「営農型太陽光発電」(以下、ソーラーシェアリング)は過去何回か取材している。(「太陽光パネルの下で神木が育つ ソーラーシェアリングの可能性」2025.01.28 「ソーラーシェアリングの課題を解決!曲がる『ペロブスカイト太陽電池』の可能性」2024.10.01)
これまでソーラーシェアリングは、主に日陰を好む植物で導入されてきた。一方、国土の狭い日本において、さらなる拡大を図るには、日光を好む植物への展開が必要だ。そのためにはパネルの影が作物に影響をあたえる可能性を考慮しなければならない。
そこで、「可動式営農型太陽光パネル」が考えられた。現在、岐阜大学と共同で実証をおこなっている。他の作物に比べ品質の影響を受けにくいとされる牧草を選んだ。日射エネルギーを生育用と発電用に配分することが可能な可動式パネルを用いて、農業と発電の両立を目指す。
可動式営農型太陽光パネル
可動式営農型太陽光パネルは、太陽の高度や方位角に応じてパネルの角度を変化させることにより、作物に対する目標遮光率(影の割合)を設定することが可能になるというもの。太陽追尾モードと太陽逆追尾モードがあり、前者は太陽光パネルが受ける日射量を最大にする角度に制御し、発電量を最大にする。後者は、太陽光パネルを農作物が受ける日射量を最大にする角度に制御する。

目標遮光率は時間帯や季節ごとに設定可能で、本実証実験では、牧草の種類や栽培工程に応じてあらかじめ検討した値を入力する。また、パネル上部と下部に日照センサーを設置し、栽培試験で得られたパラメーターを入力して試験を繰り返して最適化を図る。営農型太陽光発電は、収穫量が2割以上減収しないことが農地法で定められており、これをみたす遮光率を明らかにするとしている。
あとがき
今回の「可動式営農型太陽光パネル」の実証は、国土の狭い日本が抱える「食料安全保障」と「エネルギー自給率向上」という二律背反の課題を同時に解く、極めて重要なフロンティアだ。
従来のソーラーシェアリングの多くが、日陰を好む作物という制約的な条件で導入されてきたのに対し、この技術は、牧草での知見を獲得することで、一部で実証が進んでいるイネなどとともに、日本の食料安全保障を支える日光を好む作物への拡大を可能にする。
さらに重要なのは、「経済性を確保できるパネル制御」だ。再生可能エネルギーの電力契約が市場価格に連動する複雑な契約へと移行する中、ただ発電量を最大化するだけでは収益は上がらない。作物の生育を守るという農業上の制約を守りつつ、電力市場価格が高い季節・時間帯に集中的に発電するための賢いアルゴリズムを確立し、農家収入と発電収益の最大化を図ることが、この実証の核となる。
また、複雑な機構を持つ可動式パネルは、初期投資が高額になる。さらに、固定式パネルよりもメンテナンス費用や修理の手間が増加する可能性があるため、長期的な運用コストを考慮しなければならない。
したがって今後は、収穫量を確保し、売電の儲けを最大化し、さらに初期投資と修理代の負担を回収する、という3つの要素の最適解をアルゴリズムに組み込むことが、普及の鍵となるだろう。
2 未来のインフラを支える:高エネルギーX線回折による非破壊評価の最前線

出典)Ⓒエネフロ編集部
ガスタービンは、ジェットエンジンと同じ原理で駆動する発電設備の中核部品だ。
その仕組みを簡単に説明する。まず大量の空気を取り込み、コンプレッサー(圧縮機)で圧縮する。圧縮された空気に天然ガスなどの燃料を噴射して燃焼させ、1,000℃をはるかに超える超高温ガスを生成する。この超高温・高圧の燃焼ガスがタービンブレードに吹き付けられ、タービンを回し、回転を発電機に伝えることで、電気が生まれる、という仕組みだ。
ガスタービンは世界中の基幹インフラで不可欠な役割を果たしている重要な設備だ。特に、高温の燃焼ガスに直接さらされる動翼(ブレード)や静翼(ベーン)といった部品は、非常に過酷な環境に置かれている。
今回、ガスタービン部品の画期的な検査方法について、詳しく話を聞いた。
ガスタービンの検査
ガスタービンの燃焼ガス温度は1,500℃を超えることがあり、部品は高熱、高圧、遠心力、振動といった複合的なストレスを常に受けている。
これらの部品には、高強度・耐熱性のあるニッケル基超合金が使われ、表面は遮熱コーティング(TBC: Thermal Barrier Coating)と呼ばれるセラミック層で覆われている。超高温にさらされ続けると、部品内部の「骨格となる金属組織」が崩れてモロくなったり、表面の「保護膜(コーティング)」の下にサビのような層ができて剥がれやすくなったりする劣化が起きる。この劣化は突然の破損に繋がりかねないため、定期的な検査をおこない、安全性を確保する必要がある。
しかし、これまでガスタービン高温部品のような高強度材料の欠陥や劣化損傷状態は、切断、研磨などの加工を経た顕微鏡観察などによって判明することがほとんどだった。

出典)Ⓒエネフロ編集部
こうしたいわゆる破壊検査は、タービンを分解し、特定の部品の一部を切り出して加工し、顕微鏡などで内部組織を観察するもので、検査した部品は再利用できないため、高価な部品を廃棄しなければならない。そのうえ、抜き取った一部の部品から同種の部品すべての取替要否を判断しなければならず、抜き取った部品の劣化具合次第でまだ寿命のある部品まで取り替える可能性があり、保守・運転コストが増大する要因となっていた。こうした課題を解決する新技術が「高エネルギーX線回折による非破壊評価」だ。
高エネルギーX線回折による非破壊評価
高エネルギーX線回折(High-Energy X-ray Diffraction=HEXRD)は、従来の課題を根本的に解決する技術だ。
検査後も部品をそのまま再使用できるため、高価なガスタービン部品を廃棄せずに済み、保守・運用コストを大幅に削減できる。また、従来のX線では難しかった、遮熱コーティング(Thermal Barrier Coating=TBC)を透過し、その下にある超合金基材の内部に到達でき、材料状態を正確に把握できる。
回折装置では、ステージにサンプルを固定する治具の変更や、5軸で動作するステージを使用することで、各種部品に対応することも可能になるという。
中央の円盤(ステージ)上に被検査物を設置し、X線を照射し「X線検出器」で観察する

この技術により、点検の仕方が根本的に変わる。これまでは、高価な部品のいくつかを破壊して調べていたのだが、これからは全ての部品を破壊せずに診断できるため、本当に寿命がきた部品だけを個別に交換できるようになるのだ。
あとがき
この技術が実用化されれば、部品ごとの劣化状態に基づいた個別最適化されたメンテナンスが可能になる。厚い層を透過して内部を非破壊で評価できる特性は、ガスタービン以外の基幹産業にも応用が期待される。
例えば、原子力発電分野や、航空宇宙産業、鉄道・自動車産業などの製品の信頼性と安全性の向上に貢献しそうだ。将来的に、より小型で高エネルギーなX線発生装置が開発されれば、現場での検査も可能になり、電力インフラを含む日本の基幹産業の効率的かつ安定的な運用に大きく貢献しそうだ。





Recommend Article / おすすめ記事

RANKING / ランキング

SERIES / 連載
- テクノロジーが拓く未来の暮らし
- IoT、AI・・・あらゆるものがインターネットにつながっている社会の到来。そして人工知能が新たな産業革命を引き起こす。そしてその波はエネルギーの世界にも。劇的に変わる私たちの暮らしを様々な角度から分析する。