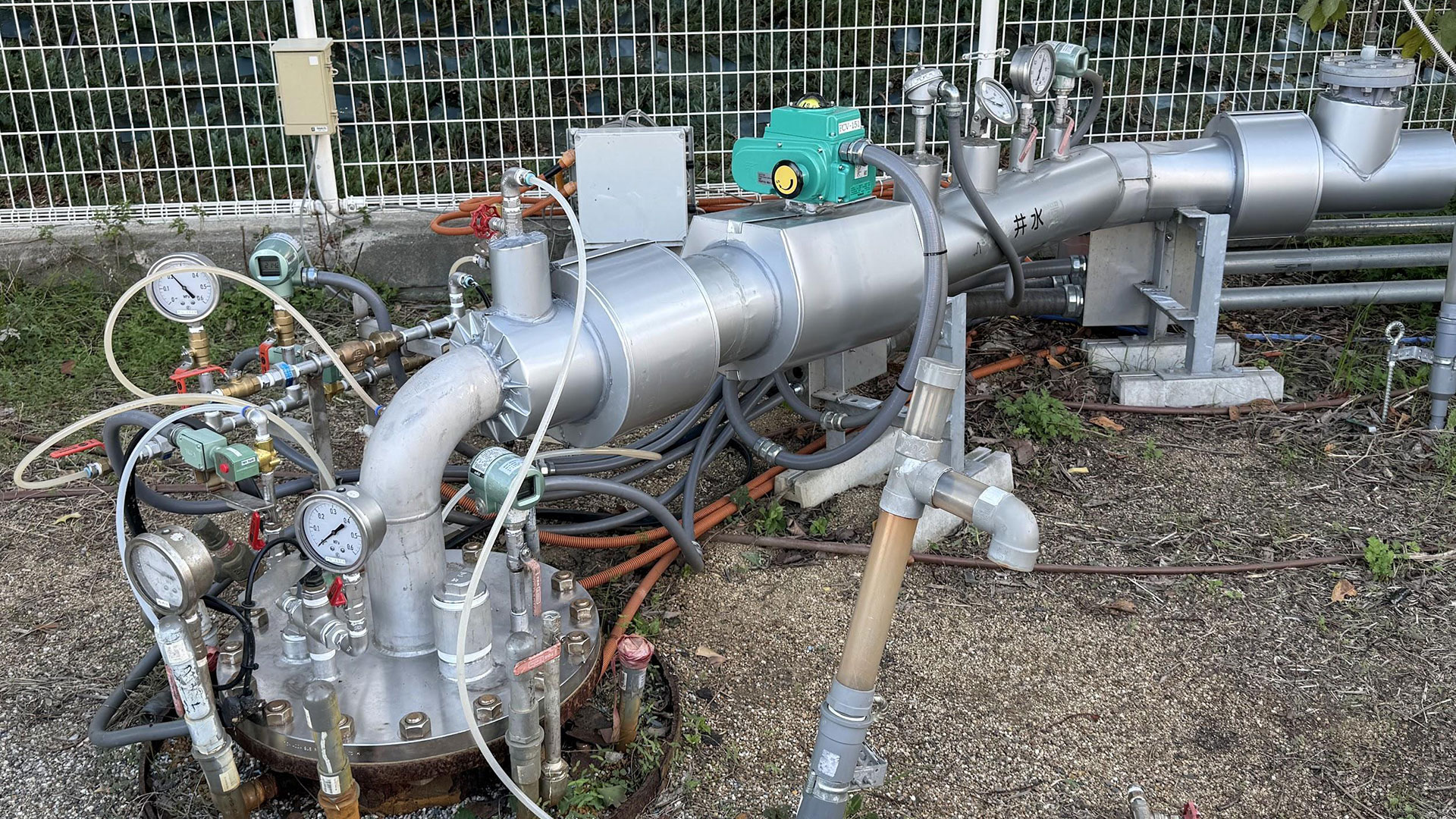写真)フィンランド南部のポルナイネン市で、稼働開始した、世界最大となる砂電池。
出典)Polar Night Energy
- まとめ
-
- 砂による蓄熱システムは、フィンランドのスタートアップPolar Night Energyが開発した「砂電池(サンドバッテリー)」。
- 再エネの安価な電力を使い、抵抗ヒーターで発生させた熱を、断熱材で覆われた巨大な鋼鉄製タンク内の砂に蓄える。
- エネルギーが必要な際には、熱せられた空気が熱交換器を通じて水を加熱し、温水や蒸気を生成する。
世界規模で再生可能エネルギー(以下、再エネ)の導入量が増えているが、太陽光発電や風力発電は、天候や季節によって発電量が大きく変動する特性を持つ。これら再エネの出力をいかに安定させ、24時間365日、信頼できる電力として供給するかが、脱炭素化社会を実現させるカギとなっている。
これまで、この課題に対する有力なソリューションは、リチウムイオン電池であった。電気自動車(EV)市場の爆発的な拡大とともに技術が磨かれ、コストが低減したリチウムイオン電池は、電力系統に接続される定置用蓄電池としても急速に普及した。
だが、リチウムイオン電池への全面的な依存は、新たな地政学的リスクと持続可能性のジレンマを生む。リチウムやコバルトといった希少資源は特定の国に偏在し、サプライチェーンは不安定さに晒される。また、数時間以上の「長時間」や、季節をまたぐ「超長期」のエネルギー貯蔵においては、リチウムイオン電池はコスト面で現実的ではない。
この課題の答えのひとつが、化学反応を利用せずに、熱や重力といった「物理法則」を利用したエネルギー貯蔵、通称「物理蓄電」だ。今回は、物理蓄電の中でもシンプルながら大きなポテンシャルを秘める「熱貯蔵」に焦点を当てる。
「熱貯蔵」といえば、以前の記事(「岩石蓄熱が拓く カーボンニュートラルの新時代」2025.04.08)で触れた「岩石蓄熱」が記憶に新しい。岩石を蓄熱媒体として利用する技術で日本で実証実験が進んでいることを紹介した。

出典)Ⓒエネフロ編集部
今回は、熱媒体に「砂」を利用した蓄熱システムを取り上げる。
砂電池の開発状況
砂による蓄熱システムを開発したのは、フィンランドのスタートアップ企業「Polar Night Energy」。あえて、「砂電池(サンドバッテリー)」と呼んでいる。
このシステムはシンプルだ。まず、再エネの発電量が需要を上回り、電力価格が低下する時間帯の安価な電力を使い、抵抗ヒーター(電気ストーブと同じ原理)で熱を発生させる(蓄熱=充電)。発生した熱は、断熱材で覆われた巨大な鋼鉄製のタンクの中に密閉された大量の「砂」に送り込まれる。タンク内の砂は、600℃程度の高温状態で熱エネルギーを蓄える(貯蔵)。そして、エネルギーが必要になった際、タンク内の熱せられた空気は、熱交換器を通じて水を加熱し、高温の温水や蒸気を生成する(放熱=放電)
Polar Night Energy社は2022年、フィンランドの西部の町カンカーンパーで最初の商用プラントを成功させた。また今年、フィンランド南部のポルナイネン市で、世界最大となる新しいサンドバッテリーが稼働を開始した。このプラントは、高さ13メートル、幅15メートルの巨大なタンクに、砕かれた滑石(ソープストーン)を蓄熱材として使用し、実に100MWhもの熱エネルギーを貯蔵する能力を持つ。市の地域熱供給網に接続されており、約1週間にわたって市の暖房をまかなうことができる。将来的に夏の間の熱を冬まで貯蔵することも視野に入れている。

以前紹介した岩石蓄熱と比べて、砂を使うメリットはなんだろうか?
砂電池の特徴
1番目は、効率的で均一な熱伝達だ。蓄熱システムは、ヒーターからの熱をいかに効率良く蓄熱材全体に伝え、またいかに効率良く取り出すかが性能を左右する。Polar Night Energyの砂電池は、タンクの内部にパイプを張り巡らせ、そこに熱した空気を循環させることで砂全体を加熱する。砂は粒子が細かく流動性があるため、空気との接触面積が大きくなり、熱がムラなく効率的に伝わる。これは、蓄熱槽内の温度を均一に保ち、安定した熱の取り出しに繋がる。一方、岩石を使う場合、岩の内部まで熱が伝わるのに時間がかかったり、岩と岩の間に不均一な隙間ができたりして、熱伝達にムラが生じやすくなる。砂を用いた方が効率良い。
2番目は、高い充填密度と体積エネルギー密度だ。同じ大きさのタンクに、どれだけ多くのエネルギーを貯められるかは重要な指標となる。砂は粒子が小さいため、タンク内に隙間なく高密度で充填することが可能で、容器の体積あたりの蓄熱量(体積エネルギー密度)が高い。同じエネルギー量を蓄える場合、より小さな設備で済む。一方、不揃いな形の岩石を積み上げると、どうしても岩と岩の間に空間ができてしまい、充填密度が低下する。その結果、同じ体積のタンクで蓄えられるエネルギー量が砂を用いる場合に比べて少なくなる可能性がある。
3番目は、ハンドリングの容易さだ。設備の建設やメンテナンスのしやすさもコストや実用性に影響する。砂は流体のように扱うことができ、ポンプやコンベアを使ってタンクへの搬入・搬出が可能だ。建設時の作業も比較的容易となる。一方、岩石を扱うにはクレーンなどの重機が必要となり、設置に手間とコストがかかる。
4番目は、用途の特化による高い総合効率だ。これは材料そのものの違いというより、Polar Night Energyの砂電池システム設計思想の優位性だ。この砂電池システムは、貯めた熱を再び電気に戻す(再電化)のではなく、地域の暖房システム(地域熱供給)へ「熱」として直接供給することを主目的としている。Polar Night Energyは、システム全体の総合エネルギー効率(往復効率 注1)が90%以上を達成することも可能だとしている。熱利用に特化した砂電池のシステムは、特定の用途において非常に高い効率と経済性を発揮するといえる。

砂電池の課題と展望
このように可能性を秘めている砂電池だが、本格的な普及に向けて乗り越えるべき課題も存在する。
課題のひとつは、大規模化と立地の制約だ。ポルナイネン市の100MWh級プラントは大きな一歩だが、大都市や大規模な工業地帯のエネルギー需要を賄うには、GWh級以上へのスケールアップが求められる。巨大なタンクを建設するための土地確保が制約となる。そして何よりも地域熱供給網というインフラが未整備の地域では、砂電池の価値は半減してしまう。
2つ目の課題は、市場と制度の未整備だ。現在の電力市場は、瞬時の需給調整能力(秒〜分単位)を評価する傾向にある。砂電池が提供する「長時間・季節間貯蔵」という価値は、まだ収益化できる仕組みが十分に整っていない。長期的なエネルギー供給安定化への貢献度を価格に反映させる「容量市場」の設計や、熱供給の価値を評価する新たな制度の創設が、普及を後押しする鍵となる。
砂電池と地域熱供給網の組み合わせは、新たなエネルギー流通網を構築する可能性がある。工場やデータセンターから出る未利用の排熱を地域の砂電池に貯蔵し、必要な時に家庭やオフィスに供給する。各地域に点在する砂電池がVPP(仮想発電所)のリソースとして連携し、広域電力網の安定化に貢献する未来も描くことができる。
砂電池。それは、リチウムイオン電池の代替を目指すものではない。これからは多様な蓄電システムが持つそれぞれの長所を活かして組み合わせる発想が注目されるだろう。その実現には、技術革新を加速させるとともに、その価値を正当に評価する市場と社会システムを構築する努力が不可欠だ。エネルギー貯蔵にかける人類の挑戦はこれからも続く。
-
往復効率(Round Trip Efficiency:RTE)
充電時にバッテリーに入力されたエネルギー量と、放電時に取り出せるエネルギー量の比率で、「放電エネルギー÷充電エネルギーx100」で求められる。





Recommend Article / おすすめ記事

RANKING / ランキング

SERIES / 連載
- テクノロジーが拓く未来の暮らし
- IoT、AI・・・あらゆるものがインターネットにつながっている社会の到来。そして人工知能が新たな産業革命を引き起こす。そしてその波はエネルギーの世界にも。劇的に変わる私たちの暮らしを様々な角度から分析する。