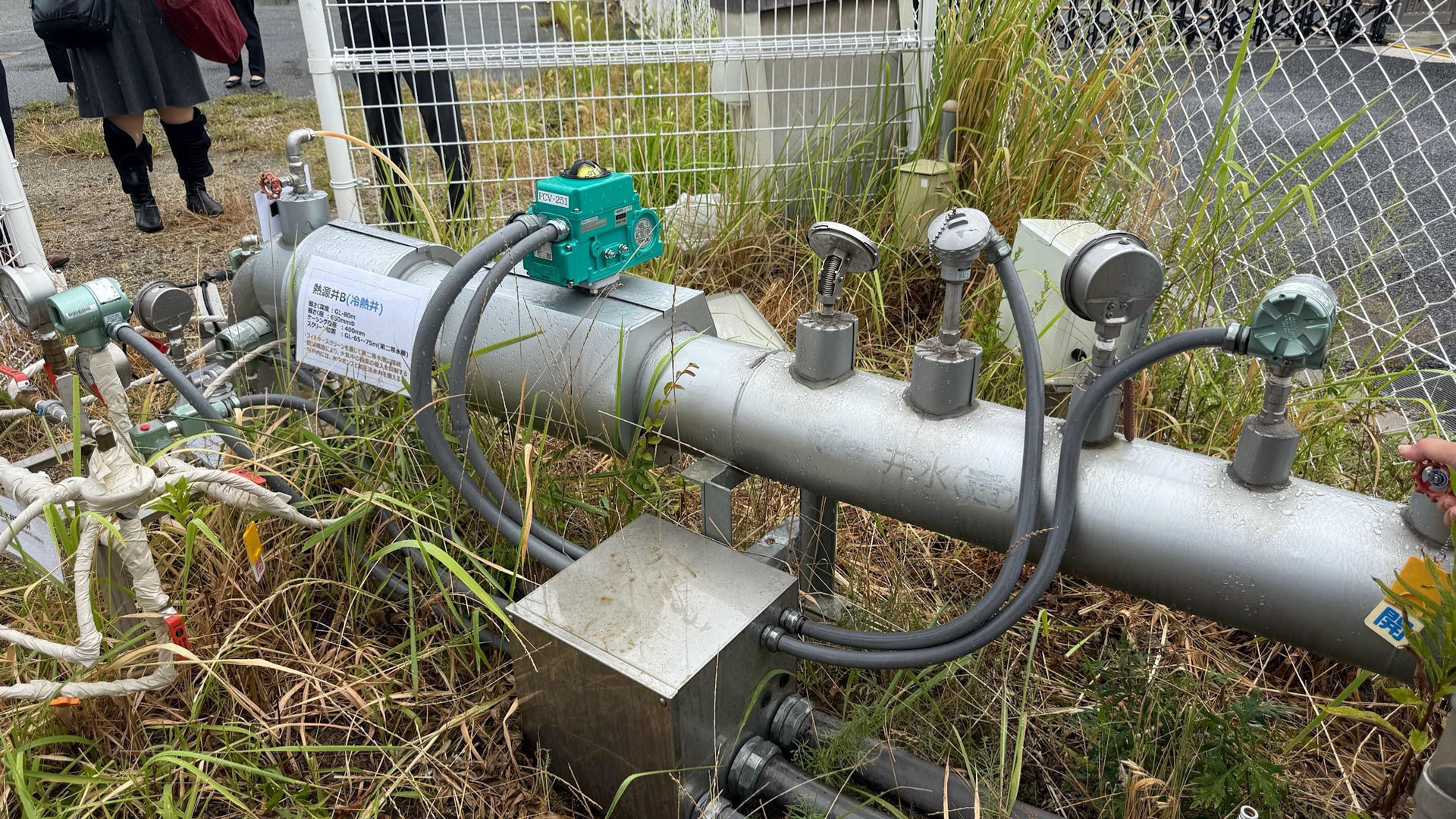写真)テスラ サイバーキャブ(ロボタクシー)
出典)Chesnot/Getty Images
- まとめ
-
- テスラ「サイバーキャブ」は、完全自動運転EVによる新たなライドシェアビジネスモデルを目指す。
- マスク氏は、ユーザーが所有するサイバーキャブをライドシェアに利用し、収益を得る仕組みを描く。
- 安全性、規制緩和、社会的受容性が今後の実現の鍵となる。
完全自動運転はまさにカーユーザーの夢だろう。ハンドルに触れることなく目的地に連れて行ってくれるなら、車のキャビンは運転する場所ではなく、リビングルームと化す。これはある意味モビリティの革命と言えるだろう。
それが今実現しようとしている。その完全自動運転EV開発の先頭を走っているのがあの、米EVメーカーのTesla(以下、テスラ)だ。
2024年10月、テスラは完全自動運転の2人乗り電気自動車「サイバーキャブ」(別名ロボタクシー)の量産を2026年に開始する予定だと発表した。価格は30,000ドル(約450万円)程度になる予定だ。2人乗りとしたのは、主に都市部での短距離移動やパーソナルな利用を想定しているからだと思われる。
サイバーキャブの特徴
サイバーキャブの特徴はいくつかあるが、まずは見る者の目を引く個性的な外観だ。その直線的でソリッドなデザインは、テスラのピックアップトラック「サイバートラック」の流れを汲んでいる。

真上に開くシザードアもあいまって、そのデザインは未来を予感させるだけでなく、頑丈さを強調している。そして驚いたことにサイバーキャブにはリアウィンドウがない。そもそも人間が運転しないので、後方を目視で確認する必要がないからだ。多数のカメラ(テスラは主にカメラを使用する「Tesla Vision」を採用)が車両の周囲360度を常時監視しており、後方の状況も正確に把握されるという。

また、サイバーキャブは非接触充電でおこなわれるため、EVには必ずついている充電ポートがない。さらにリアウィンドウがないことで、より統一感のあるパネル構造と洗練された流れるようなデザインが可能になった。リアウィンドウを無くしたことで、ガラスやワイパー、デフォッガー(ガラスに埋め込んだ電熱線を熱して曇りを取る機構)などの部品が必要なくなり、製造コストの削減、車両重量の軽量化、構造の簡素化が可能になった。乗客のプライバシーも守られるほか、断熱性、遮音性も向上するものと思われる。
次にインテリアを見てみよう。当然だが、運転席にはステアリングやアクセルがない。既に販売している「Model 3」や「Model Y」に似たダッシュボードを備え、中央に大型ディスプレイが備え付けられている。テスラらしいシンプルなデザイン哲学が徹底されており、物理ボタンや複雑な操作系はほとんどない。

また、自動清掃システムが採用されるようだが、その詳細は不明だ。ユーザーとしては、フロアマットの汚れの掃除は面倒なので、車が勝手に清掃してくれるならこんな便利なことはないだろう。
内装の詳細に関しては、以下の動画をご覧いただくとわかりやすいだろう。「運転する」場所ではなく「移動する」ための快適で効率的な空間として徹底的に最適化され、未来のモビリティサービスを予感させるデザインだ。
サイバーキャブの自動運転レベルは、レベル4(高度運転自動化)以上で、すでに今年6月22日から、テキサス州オースチンの一部地域で試験的に配車サービスが始まっている。テスラのHPによると、ユーザーはまずロボタクシーアプリをダウンロードし、目的地を入力すると、乗車料金と車両が到着するまでの予想所要時間が表示される。車両が到着したら、ナンバープレートの番号と車両番号を確認し、乗車するだけであとは目的地に勝手に連れて行ってくれる、というわけだ。現時点のサービス提供地域での料金は、定額制で極めて安く抑えられているという。
ジャーナリストやYouTuber向け実車レポートを見ると、実際に運用されているのはサイバーキャブではなく、既存のミッドサイズSUVであるモデルYを自動運転用に改造された車が使われている。また、助手席に自動運転システムを監視し、必要に応じて介入するセーフティードライバーが座っている。実際に稼働しているのはまだ10台程度にとどまっており、慎重にスタートを切った模様だ。
しかし、実際に実車した一部メディアの論調は辛口だ。「交通違反や急ブレーキが頻発した」(The Gurdian 2025.6.29)ことから、「NHTSA(米運輸省道路交通安全局)がテスラに情報提供を求めている」との報道もあった。(The Gurdian 2025.6.24)
また、テスラが完全自動走行に、カメラのみを用いて道路状況を読み取る手法をとっていることに疑問を呈する論調もある。競合他社はカメラに加え、レーザー光で距離を測るLiDAR(ライダー)やレーダーシステムを搭載しており、テスラのシステムより高精度に周囲の状況を把握できるというのだ。(Reuter 2025.6.23)
完全自動運転車サービスで先行するライバルのGoogle系Waymoに比べ、テスラのサービスは出遅れた、との論調が多い印象だ。
サイバーキャブの目指すビジネスモデル
確かにテスラは、完全自動運転車のサービスの開始で、ライバル達に遅れを取った。しかし、これが最も重要なのだが、マスク氏はサイバーキャブを単なる配車サービス用EVとして開発したのではない、ということだ。
どういうことかというと、氏はサイバーキャブのユーザーが自身の保有しているサイバーキャブをライドシェアに利用することを想定しているのだ。つまり、ユーザーが保有する車が勝手にお金を稼いでくれるという全く新しいビジネスモデルを構築しようとしている。テスラとサイバーキャブのユーザーの間でどう収益を分配するかなどは明らかになっていないが、理論的には不可能でないように思われる。
サイバーキャブ以外に、より多くの人を乗せることができるロボバン(Robovan)も発表されており、将来的に完全自動運転車を使ったライドシェア経済圏を全米に拡大していく野望をマスク氏は抱いているようだ。
テスラの優位性は、車両の設計、部品製造、ソフトウェア開発、販売、充電インフラの構築など、自動車生産に関わるほとんどすべての工程を自社で一括して手がける「垂直統合型テクノロジー」にある。また、すでに米国内で100万台以上走っているテスラ車から得られる走行データは、ライバルのそれを凌駕し、完全自動運転機能の進化を加速させることができる。さらに、複雑なセンサー類を使わず、ステアリングやペダルがないなど、車両価格を大幅に削減できることも強みだとみられている。
先に述べたテスラ車を使った新たなビジネスモデルに興味を持つユーザーが急速に増える可能性もあり、それはマスク氏が描く完全自動運転車を核としたビジネスモデルにとってプラスに働く。したがって、現時点のテスラの出遅れをもってして、必ずしもその競争優位性が劣後しているとは言い切れない。実際、マスク氏はこれまでも不可能を可能にしてきており、テスラ株の今後の上昇は固いと予測するアナリストもいる。(Seeking Alfa 2025.6.26)

テスラには、中国の自動車メーカーというライバルもいる。完全自動運転車市場の国際競争はますます激しさを増すだろう。日本でも自動車メーカーやベンチャーが、同分野での技術開発に力を入れているが、果たして米中のライバルに追い付き追い越すことができるのか、引き続きその推移を見守りたい。





Recommend Article / おすすめ記事

RANKING / ランキング

SERIES / 連載
- テクノロジーが拓く未来の暮らし
- IoT、AI・・・あらゆるものがインターネットにつながっている社会の到来。そして人工知能が新たな産業革命を引き起こす。そしてその波はエネルギーの世界にも。劇的に変わる私たちの暮らしを様々な角度から分析する。