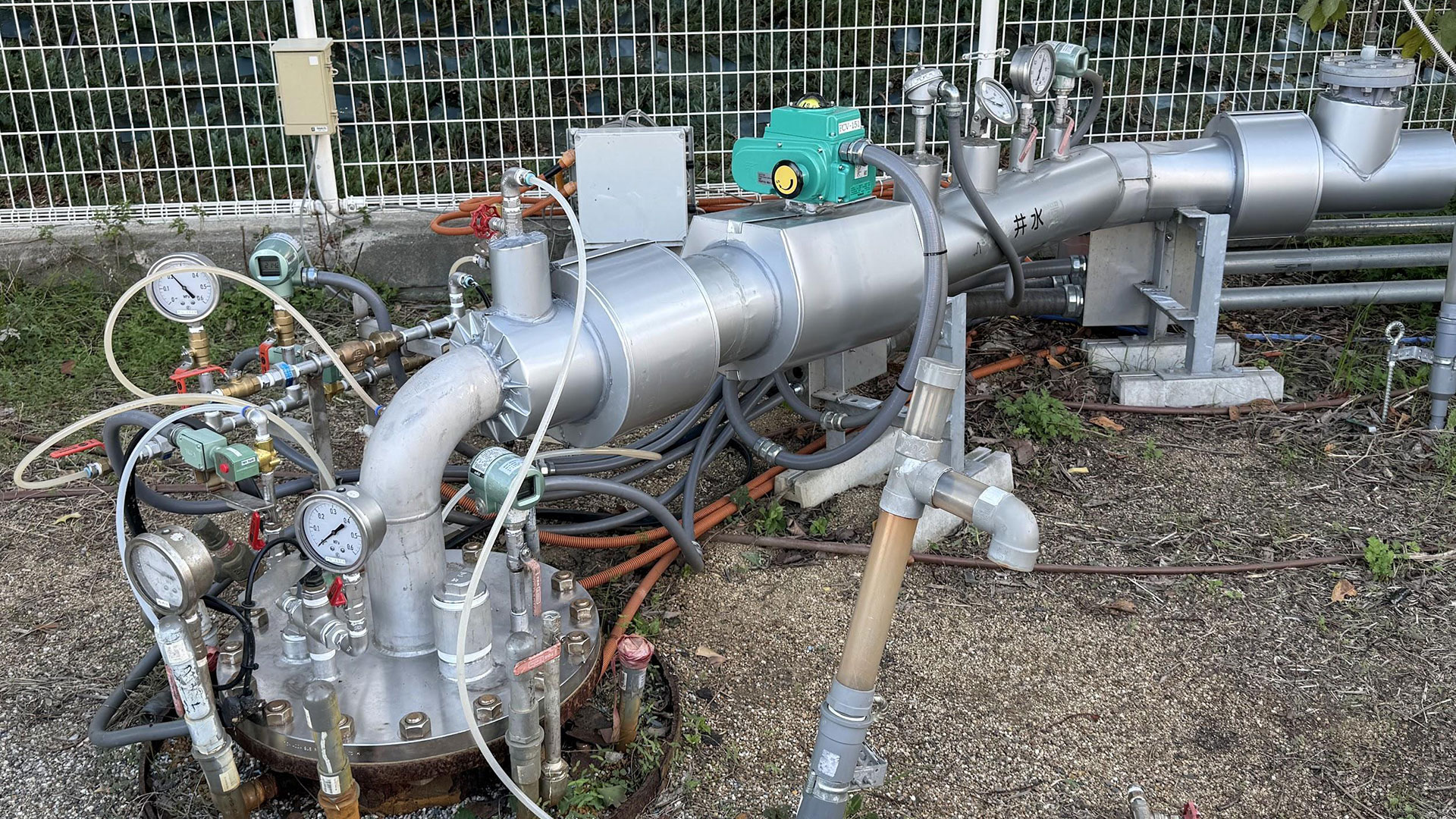写真)イメージ
出典)Galeanu Mihai/GettyImages
- まとめ
-
- 中部電力ミライズが提供する「カテエネBANK」は、エネルギー情報と金融情報を組み合わせた新しい金融サービス。
- 住信SBIネット銀行との提携により、顧客のエネルギー管理と金融管理の一元化を図る。
- エネルギーデータと金融データを連携させることで、独自の価値を提供し、顧客エンゲージメントの深化と新たな事業領域への挑戦を目指す。
電力会社が銀行サービスを始めたと聞いて興味が湧いた。中部電力ミライズ株式会社(以下、中部電力ミライズ)が2024年12月に本格展開を開始した「カテエネBANK」がそれだ。
「カテエネBANK」は単なる銀行アプリではない。エネルギーと金融を掛け合わせたユニークな価値提供を目指している。なぜ今、電力会社が金融なのか。その背景にある戦略と、サービスが目指す未来について、開発を主導した中部電力ミライズ株式会社リビング営業本部長八木貴央氏に話を聞いた。

出典)Ⓒエネフロ編集部
カテエネBANKとは:暮らしに欠かせないエネルギーと銀行サービスをセットで提供
もともと中部電力ミライズは、家庭向けWEB会員サービス「カテエネ」を通じて、電気・ガス使用量の見える化やお得なポイントサービスを提供している。
「カテエネBANK」は、その「カテエネ」の会員を対象とした新たな金融サービスだ。最大の特徴は、中部電力ミライズの電気・ガス料金をカテエネBANKで支払うことで最大5%のカテエネポイントの還元が得られる点だ。ポイントは電気代の支払いや15種類以上の他社ポイント(dポイント、Vポイントなど)に交換可能で、まさにエネルギーと銀行のセット割だ。
そのほか、以下のサービスがある。
1 振込手数料・ATM手数料は月5回無料(提携ATM:セブン銀行、ローソン銀行など)。
2 スマホ完結:アプリで口座開設(最短即日)、残高照会、デビットカード(Mastercard®、スマホタッチ決済対応)利用、ATM操作(キャッシュカード不要)。
3 便利機能:目的別口座(最大10個)、SBI証券連携、引落し前通知。

出典)中部電力ミライズ株式会社
ローンチから約半年が経過したが、ポイント還元やキャンペーンにより、顧客からはポジティブな反応が得られているといい、3年の間に10万件の契約者数の目標に着実に向かっている。
中部電力ミライズは、カテエネBANKのサービス開始にあたり、住信SBIネット銀行株式会社(以下、住信SBIネット銀行)と提携し、同社を所属銀行とする銀行代理業者の許可を取得したが、八木本部長はその背景として、「住信SBIネット銀行さまはネット銀行として先駆的に事業に着手されており、BaaS(バース):Banking as a Service(バンキング・アズ・ア・サービス)(注1)の分野で圧倒的なシェアを持っている。また最新のテクノロジーを活用しつつ、お客さま目線で当社と共にサービスを追及してくれるところに魅力を感じました」と述べた。

出典)Ⓒエネフロ編集部
カテエネBANKの特徴:エネルギーデータとの連携が生む独自の価値
カテエネBANKは単なる銀行アプリに留まらない。
八木本部長は、「カテエネをエネルギーの見える化サービスから、お客さまの暮らしに欠かせないサービスプラットフォームへと進化させたい」と意欲を示す。電気・ガスといったエネルギー情報に加え、金融という暮らしに不可欠な情報を同じプラットフォームに統合することで、これまでは別々に管理されていた「エネルギーと暮らしのお金」に関するデータを連携させ、新たな価値を創出することを目指しているのだ。
また、中部電力ミライズが保有する顧客の詳細なエネルギーデータと、その利用者の金融データを掛け合わせることができる点も、今後、電力会社ならではのサービス提供につながり得る。
「私たちはスマートメーター(注2)の普及により、30分ごとの詳細な電気使用量データを保有しています。これは他の金融サービスにはない、我々ならではの強みです」と八木本部長は強調する。
開発の経緯:顧客エンゲージメントの深化と新たな事業領域への挑戦
ミライズはなぜカテエネBANKの開発に踏み切ったのか。その背景には、電力小売全面自由化以降、激化する顧客獲得競争と、エネルギー業界を取り巻く環境変化がある。
八木本部長は、開発の動機を次のように語る。
「電力自由化以降、お客さまとの接点は『電気を使っていただく』という一点に留まりがちでした。しかし、カーボンニュートラルの実現やライフスタイルの多様化が進む中で、エネルギーサービスも変革を迫られ、お客さまの暮らし全体に寄り添い、より深いエンゲージメントを築くために、エネルギー以外の領域でもお役に立つ必要が出てきたのです」。

出典)Ⓒエネフロ編集部
従来、電力会社と顧客の関係は、月に一度の検針と料金請求が中心であり、その接点は限定的だった。しかし、カテエネBANKを通じて金融というユーザーにとって日常的に関心の高い情報を提供することで、顧客との接触頻度を高め、サービスに対するロイヤリティ(愛着)を向上させる狙いがある。日々の家計管理のためにサービスを利用してもらう中で、自然な形で中部電力ミライズのエネルギーサービスや新たなソリューションに触れてもらう機会を創出するのだ。
これは、中部電力グループが目指す「エネルギープラットフォームとデータプラットフォームの融合によるサービス実現の加速」という、より大きな事業戦略の一環でもある。エネルギー供給で培った顧客基盤とデータ活用ノウハウを活かし、金融、ひいては暮らしに関わる様々なサービス領域へと事業を拡大していく。カテエネBANKは、そのための戦略的な布石といえよう。(参考:「中部電力グループ経営ビジョン2.0」第2章 2030年に向けた取り組み、 参考記事:DX人財倍増の600人超へ。基盤領域が厚くなるほどDXの可能性が生まれる」中部電力伊藤久德取締役専務執行役員経営戦略本部長、CIO 2022.02.22)
今後の課題と展望
大きな可能性を秘めるカテエネBANKだが、その成功にはいくつかの課題もある。
最大の課題は、言うまでもなく「信頼の獲得」だ。特に、電気代や資産情報という極めて重要な個人情報を預かることになるため、顧客からの絶対的な信頼が不可欠となる。堅固なセキュリティ体制の構築と維持はもちろんのこと、何のために、どのデータを、どのように使うのか、といったデータ活用の透明性を丁寧に説明し、顧客の理解と納得を得るための継続的なコミュニケーションが求められる。八木本部長も「お客さまの大切な情報をお預かりする重みを常に意識し、信頼を裏切らないことを最優先に事業を進めていかなければならない」と気を引き締める。
また、数多ある金融サービスとの競争の中で、いかにして「選ばれ、使われ続けるサービス」になるかという点も重要な課題だ。そのためには、UI/UX(注3)の継続的な改善はもちろんのこと、「エネルギーデータとの連携」という独自の強みを、顧客にとって真に価値のある機能へと進化させ続ける必要がある。
カテエネBANKについて、八木本部長は住信SBIネット銀行との連携を強化し、サービス拡充を目指す考えを示した。
すでにカテエネBANKでは、住宅ローンの利用で電気・ガスの支払いから5%ポイント還元サービスを提供しているが、八木本部長は、「電気料金を毎月払っていただいている方はローンの条件をよくすることなどが実現できたらいいと思います。もともとネット銀行はいろいろな融資の仕組みを持っているので、それと我々が持っているデータと掛け合わせて、お客さまに利便性やメリットを提供していきたい」と述べ、住信SBIネット銀行が持つノウハウと中部電力ミライズのデータを組み合わせることで、新たな価値を顧客に提供していく考えを明らかにした。
インタビューを終えて(編集後記)
エネルギーデータと金融データを掛け合わせは、他にはない、金融サービスの提供につながるポテンシャルがあると感じた。
例えば、太陽光発電や蓄電池、EV(電気自動車)といった分散型エネルギーリソース(DER:Distributed Energy Resources)の普及が進む中で、その経済効果を可視化する上で、この連携は大きな意味を持つと考える。太陽光発電による売電収入や、EVの充電による支出、V2H(Vehicle to Home)(注4)を活用した際の電気代削減効果などを、家計全体の資産状況と合わせて一元管理できるようになれば、利用者は、自身のエネルギー関連設備の経済価値を直感的に把握し、より最適なエネルギーマネジメントをおこなうことができるだろう。
エネルギーと金融の融合が、私たちの暮らしを、そして社会を、より効率的に、より環境に優しいものに変えていこうとしている。今後、どんなサービスが登場するのか、期待しながら注視したい。
-
BaaS
銀行が提供する金融機能をAPIなどを介して、他の企業や組織が自社のサービスやシステムに組み込んで利用できるようにする仕組み。 -
スマートメーター
電力使用量をデジタルで計測し、双方向通信機能を備えた電力メーター。30分ごとの電気のご使用量を計測することができ、かつ通信機能を保有している。 -
UI/UX
UIは「User Interface(ユーザーインターフェース)」の略。ユーザーとサービス・製品との接点(のことで、Webサイトやアプリのボタンの大きさや操作のしやすさ、画像の見やすさやページの表示速度などがあげられる。
UXは「User eXperience(ユーザーエクスペリエンス)」の略。ユーザーがサービスや製品の使用で得られる体験のことで、商品やサービスそのものに対する感想や評価などが含まれる。 -
V2H(Vehicle to Home)
電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド車(PHEV)に蓄えられた電力を自宅で利用したり、太陽光発電などの住宅用発電システムでEVを充電したりする機器やシステム。





Recommend Article / おすすめ記事

RANKING / ランキング

SERIES / 連載
- エネルギーと私たちの暮らし
- 私達が普段なにげなく使っている電気。しかし、新たなテクノロジーでその使い方も日々、変化しています。電気がひらく「未来の暮らし」、覗いてみましょう。