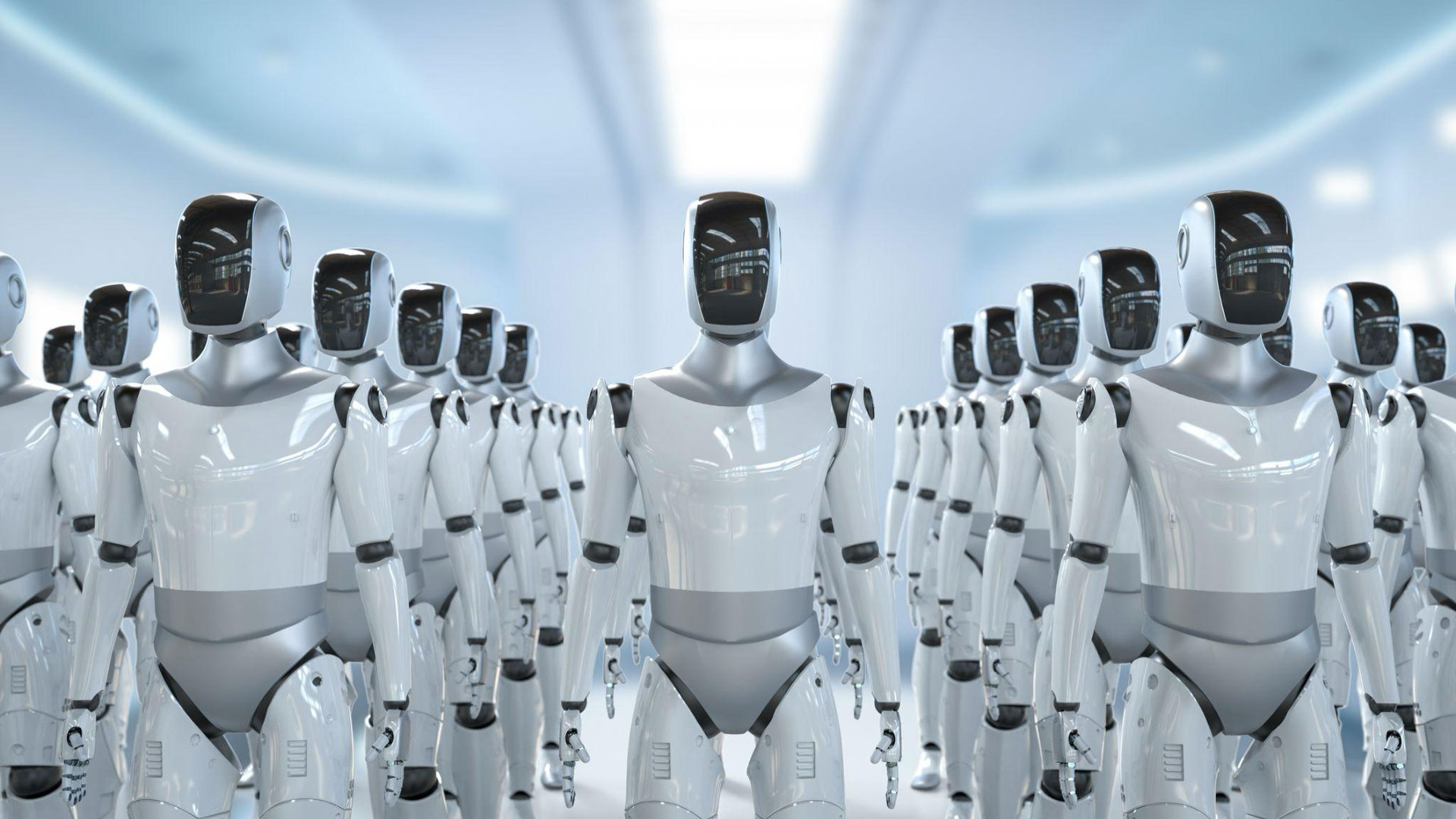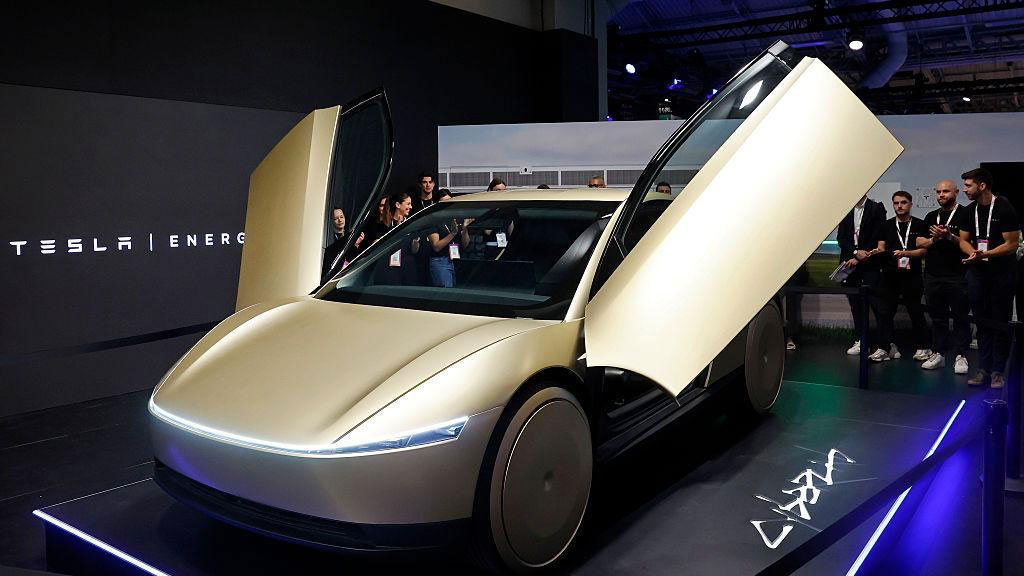写真)日本で走行するWaymoのロボタクシー
出典)日本交通株式会社
- まとめ
-
- Waymoらが東京でロボタクシー実証実験を開始。都心7区でテスト走行。
- 技術的課題、法規制、インフラ整備、コスト、社会的受容性など、実用化には多くの課題が。
- 日本でのレベル4自動運転サービスの普及には、少なくともあと3年はかかると予想される。
自動運転技術、特にドライバーレスで運行するロボタクシーの現状については以前紹介した。(「加速する自動運転 日本の現状は?」2024.04.09)
全国で自治体が主導して自動運転バスなどの実証実験をおこなっている例は増えているが、まだ自動運転レベル2の段階であり、レベル4のロボタクシーが商用化されている米中と比べると遅れている状況であった。しかしその波がついに東京へとやってきた。少子高齢化に伴うドライバー不足といった日本特有の社会課題を解決するブレークスルーとなり得るのか、東京におけるロボタクシー開発の最前線について見ていこう。
東京、ロボタクシー革命の最前線へ
東京がロボタクシー開発の新たな舞台になりつつある。Googleの親会社Alphabet Inc.の子会社、Waymoや、株式会社ティアフォー(以下、ティアフォー)、日産自動車株式会社など、国内外の企業が実証実験や事業化計画を着々と進めている。
ティアフォーはお台場での事業化計画を発表し、西新宿で実証をおこなった。日産は横浜での運転席無人走行実験を成功させ、具体的なサービスロードマップを提示した。一方、ホンダがGM・Cruiseと共同で進めていた2026年の都心サービス開始計画は、GMのロボタクシー事業撤退により先行き不透明な状況になっている。
そうしたなか、タクシー会社とアメリカのロボタクシー企業がタッグを組み、実証実験に乗り出したことに注目が集まっている。4月14日、Waymoは、モビリティ関連企業のGO株式会社(以下、GO)、日本交通株式会社(以下、日本交通)と提携し、都心部で試験走行を開始すると発表した。
Waymoのロボタクシー実証実験の中身
Waymo、GO、日本交通3社が開始した実証実験は、初期テストフェーズとして、都心7区(港区、新宿区、渋谷区、千代田区、中央区、品川区、江東区)において、まずは、日本交通の乗務員が運転するWaymoの自動運転車両(Jaguar I-PACEベース)をテスト走行させる。テスト車両の屋根や車体周囲には、LiDAR(レーザー光で対象物までの距離や形状を高精度に測定するセンサー)、カメラ、レーダーなどが搭載されている。

© 日本交通株式会社
無人のロボタクシーが公道を走り回っている様子は日本人には想像もつかないが、Waymoはすでに米国内(アリゾナ州フェニックス、カリフォルニア州サンフランシスコ・ロスアンゼルスなど)でサービスを開始している。今回の東京での試験走行は米国以外で初めてとなる。
今回の実証では、手動運転で収集するデータを活用し、Waymoの自動運転技術を日本向けに適応させていく。具体的には高精度3次元地図データの収集、日本の道路標識や交通ルールなどの特有環境の定義、そしてWaymoのソフトウェア、「Waymo Driver」の日本公道条件への適合性検証である。
気になる自動運転サービスの開始時期だが、今のところ「未定」だということだ。3社は関連省庁、警察、自治体などとも進捗段階に合わせてきめ細かく連携していく予定だ。
自動運転の課題と実用化への道筋
完全自動運転は、交通安全の向上、移動の利便性向上、物流効率化、ドライバー不足問題の解消など、社会に大きな変革をもたらす可能性があり、実用化への期待が高まっている。しかし、その実現には多くの課題がある。細かく分けると、技術、法規制、インフラ、コスト、社会的受容性の5つの側面がある。
A. 技術的課題
複雑な交通環境(都市部、悪天候、歩行者等の予測不能な動き)への完全な対応、稀な事態(エッジケース)への対処能力、AIの判断プロセスの信頼性、そして高度なサイバーセキュリティの確保が求められる。
アメリカの自動車メーカーGMの関連会社であるCruiseが2023年に起こした事故は、人間の運転する車にはねられ飛ばされてきた女性と衝突したCruiseの自動運転車が、衝突後に停止せずに路肩へ移動しようとして、下に巻き込んだ女性を約6メートル引きずってしまったというものだった。こうした事態も含め、あらゆる事態に対応することが求められるだけに、技術的なハードルは依然として高い。
B. 法規制・法的課題
事故発生時の責任所在の明確化も重要な課題だ。自動車保険のあり方にも大きな影響を与えることになる。また、レベル4での運行の許認可の基準や、収集される膨大なデータのプライバシー保護と利活用ルールの策定、国際的な技術・安全基準との整合性も不可欠だ。
C. インフラの課題
インフラについては、高精度3次元地図の整備・維持コストが大きな課題となっている。また、安全性を向上させるために必要なV2X(車車間・路車間通信)連携のために、信頼性の高い大容量通信網(5G/6G)整備することや、走行する車両と無線通信をおこなうための装置(路側機)などのインフラ設置が必要となり、これらのコストも課題となる。
D. コスト面の課題
高性能センサーやコンピュータなどによる車両・システムコスト、巨額な研究開発・検証コスト、インフラ整備・維持コストが重くのしかかる。これらの投資を回収し、既存交通サービスと競争可能な価格でサービスを提供できる持続可能なビジネスモデルの確立が求められる。
E. 社会的受容性・倫理的課題
ドライバーが運転しない車両への一般市民の安全に対する不安感を払拭し、信頼を得ることが普及への鍵となる。そのためには、事故情報の透明性確保が求められる。また、避けられない事故における倫理的判断への社会的合意形成も課題となる。これらの課題については、社会全体でのオープンな議論やルール作り、丁寧なコミュニケーションを通じて、合意形成を進めることが求められる。
実用化のタイムスケジュール
以下はあくまで筆者の予測であるが、日本での実用化は段階的に進むと予想される。ざっくりいうと、レベル4の自動運転サービスの普及には、最低でもあと2,3年はかかるのではないか。
- ● 2025年度~2026年度:
- ○ 高度運転支援(レベル2/3)が各地域に普及。
- ○ レベル4は、限定された地域・ルート(低速シャトル、特定施設内など)での実証実験が中心。
- ○ 都市部での実証はデータ収集や限定テスト走行が主となり、広範なサービス提供はまだ先になる
- ● 2027年〜2030年頃:
- ○ 限定エリア(都市特定ゾーン、高速道路本線など)でのレベル4サービス(ロボタクシー、トラック)が徐々にスタートする。ただし運行条件(エリア、時間、天候)は限定的。
- ○ 大都市中心部での広範なドライバーレスサービスの一般化は依然困難と予想される。
- ● 2030年以降:
- ○ 技術・コスト・インフラ・制度等が順調に進展すれば、レベル4の適用範囲が拡大する可能性がある。
保守的な予測に思えるかもしれないが、安全基準などに厳しい日本の法規制などを踏まえると、このぐらいのタイムスパンで進むものと思われる。
以上見てきたように、完全自動運転のロボタクシーは大きな可能性を秘めている一方、数々の課題を抱えている。繰り返しになるが、日本の場合は、米中のように普及ありきではなく、実用化に向け段階的なプロセスを踏むだろう。特に東京のような複雑な大都市での全面展開には、さらなる時間と慎重な検証が必要だ。研究開発とともにコスト削減を進め、同時に、法制度、インフラ整備、そして社会との対話を通じた信頼醸成を進めることが不可欠だ。





Recommend Article / おすすめ記事

RANKING / ランキング

SERIES / 連載
- テクノロジーが拓く未来の暮らし
- IoT、AI・・・あらゆるものがインターネットにつながっている社会の到来。そして人工知能が新たな産業革命を引き起こす。そしてその波はエネルギーの世界にも。劇的に変わる私たちの暮らしを様々な角度から分析する。