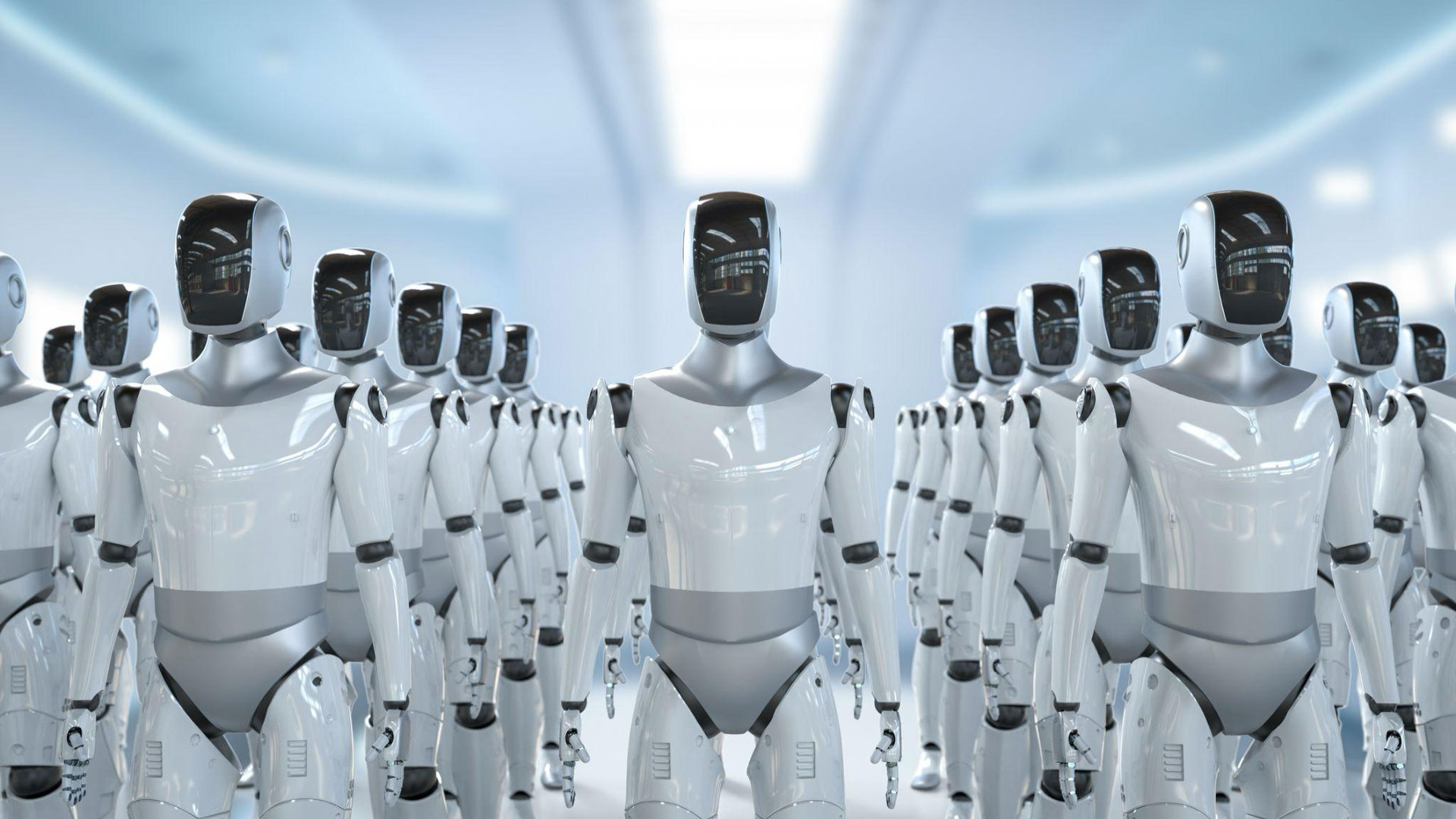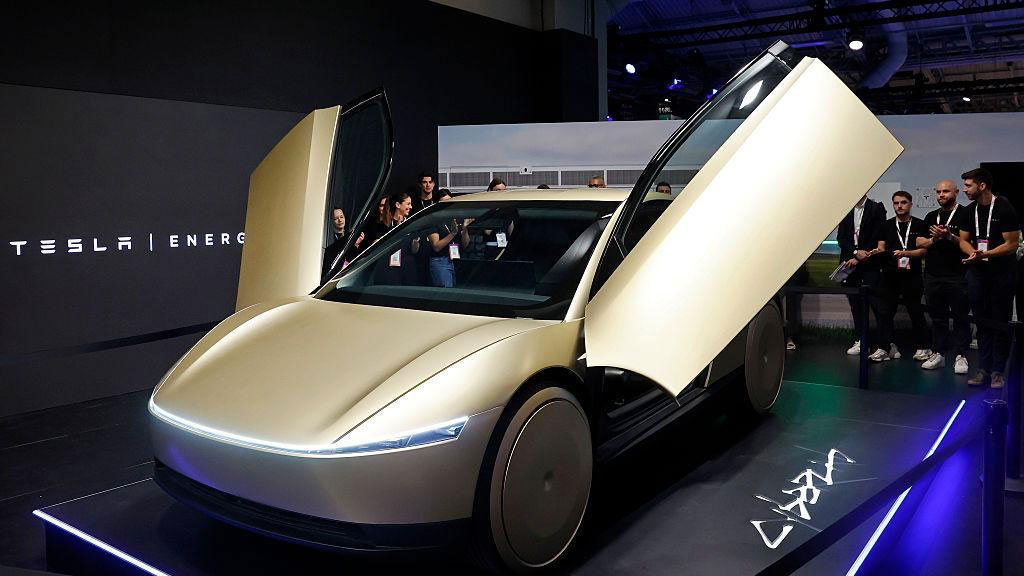写真)地球深部探査船「ちきゅう」
出典)©JAMSTEC
- まとめ
-
- レアアースはハイテクやクリーンエネルギー分野に不可欠で、中国の供給支配が国家安全保障上のリスクとなっている。
- 日本は南鳥島沖のレアアース深海泥の国産資源開発を計画、2026年1月には探査船「ちきゅう」による試掘が計画されている。
- このプロジェクトは技術的課題や環境問題、国際規制との整合性などの課題を抱えつつも、日本の経済安全保障と産業競争力強化に貢献する可能性を秘めている。
今、レアアース(希土類:注1)が世界的に注目を集めている。その理由はさまざまだ。
第1に、レアアースがハイテクやクリーンエネルギー分野に欠かせない素材であることが挙げられる。その用途は幅広く、電気自動車(EV)、風力発電、スマートフォン、半導体、医療機器(MRI)、高効率照明(LED)など多岐にわたる。産業の国際競争力を維持するために不可欠なものだ。
第2に、中国のレアアース供給支配と地政学的緊張がある。中国は世界のレアアース生産の約70%(27万トン/2024年)、精錬の実に約90%を握る。また、その埋蔵量は4,400万トンと推定されており、これは世界総量の34%にも相当する。
この偏重した供給構造は、国家安全保障上の大きなリスクである。実際、2010年には尖閣諸島の領有権問題を背景に、中国は日本向けのレアアース輸出を停止し、価格変動を引き起こした過去がある。また直近では今年4月、中国がトランプ関税の対抗措置として、7種のレアアースについて輸出管理を強化し、レアアース国際供給網のさらなる不安定化を招いたことは記憶に新しい。資源の「外交カード化」が現実の脅威となっている。
日本周辺の潜在的な埋蔵量は?
このような外的リスクに対抗する手段として期待を集めているのが国産レアアース資源の開発だ。なかでも注目されているのが、南鳥島沖の排他的経済水域(EEZ)内の海底に広がるレアアースを含む深海泥だ。
この海域には、ジスプロシウムなどの重希土類を中心に、産業的規模の開発ができる埋蔵量が見込まれており、加えてコバルトやニッケルといった重要金属も豊富に含まれているとされる。これは日本が将来的にレアアースの自給自足体制を構築し、中国への依存からの脱却を図れるかもしれないことを示唆している。

出典)海上保安庁ホームページ
探査船「ちきゅう」によるレアアース回収事業
この戦略的資源開発は、内閣府戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)の主導で進められているが、この中核となるのが、海洋研究開発機構(JAMSTEC)の地球深部探査船「ちきゅう」である。「ちきゅう」は、海底下をより深く掘削するために、世界で初めてライザー掘削技術(注2)を導入した科学掘削船で、世界最高の掘削能力(海底面下7,000m)を有しており、巨大地震発生のしくみ、将来の地球規模の環境変動の解明、海底下生命圏をはじめとする未踏のフロンティアへの挑戦など、さまざまな掘削航海をおこなっている。
この「ちきゅう」の能力を活かし、2026年1月に南鳥島沖の水深5,500mの海底からレアアース泥を回収し、採鉱システムの実証を行う計画である。

この試験は、世界初の超深海からのレアアース泥を回収するための商業採掘前提の技術検証であり、採算性よりも将来的に持続可能な開発の可否を探ることを目的としている。今回の試験が成功すれば、2027年には1日最大350トン規模での回収システムの試験へとスケールアップし、2028年以降商業化の段階に移行する計画であり、将来的には民間企業の参入も視野に入れている。
課題と今後の展望
しかし、このプロジェクトにはいくつかの課題もある。まず、技術的なハードルだ。5,500mという超深海での採掘には、高圧環境に耐える堅牢な採掘機器の開発が必要なことに加え、研磨性の高い海底泥を海面まで送る技術の確立や、機器の耐久性、安全性確保といった深海特有の課題が山積している。
また深海採掘に関しては、国際海底機構(ISA)による規制の整備も進められており、日本のEEZ内とはいえ国際的なルールとの整合性が問われている。
環境保全の観点からは、未解明な部分が多い深海生態系への影響を懸念する声もあり、国際社会では20か国以上が深海採掘の猶予措置を求めており、日本の開発姿勢も注視されている。
あとがき
南鳥島沖のレアアース開発は、日本にとって単なる資源採掘を超えた経済安全保障・産業競争力・技術主導の国家戦略としての意義を持つ一大プロジェクトである。
成功すれば、資源の国産化と備蓄強化による供給安定や中国依存からの脱却、民間企業を巻き込んだ新たな海洋資源産業の創出など幅広い利益が期待される。資源のサプライチェーンが刻一刻と変化するなか、本プロジェクトの推進は遅滞なく進められなければならない。
一方で、深海環境との共存や国際的な信頼構築といった側面にも十分な配慮が求められることも事実だ。「持続可能な資源開発」と「国際的な責任あるプレーヤーとしての姿勢」を両立できるかが今後の鍵となるだろう。
-
レアアース
元素周期律表の原子番号57番から71番までの15元素と21番のスカンジウム(Sc)、39番のイットリウム(Y)を加えた17元素の総称。1794年発見当初、希少な物質であるとされていたことから、レア(稀)なアース(土類)と呼ばれたことが語源だ。鉱石からの抽出や元素ごとの分離が困難であることから希少とされている。 -
ライザー掘削
掘削時にドリルパイプとライザーパイプを2重構造にすることで泥水を循環させ、掘削孔を壊さず大深度の掘削を可能とする技術。





Recommend Article / おすすめ記事

RANKING / ランキング

SERIES / 連載
- エネルギーと私たちの暮らし
- 私達が普段なにげなく使っている電気。しかし、新たなテクノロジーでその使い方も日々、変化しています。電気がひらく「未来の暮らし」、覗いてみましょう。